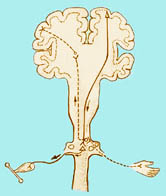��2�� �@��\���I�����w�Ɛl�ԗ����i���j
�@ �@�@�@�@�@�@J�E���m�[�w���R�ƕK�R�x���߂�����
�e�L�X�g P.61�`P.68
�@�@���m���̗ϗ�
�@�@�����m�[���_�̞B����
�@�@���_�ɋF���ĎE��
���R�Ȋw�̔F�����[�܂邱�Ƃɂ���Ă���܂ł̕������I�̌n�͗h���Ԃ��������ꂽ�B
| �������I�̌n | �ϗ��ƒm���͊����Ȃ��B���݂ɐZ���B |
| ���R�Ȋw �i�q�ϓI�m���j |
�����Ɖ��l�̋敪��v������B �����Ɖ��l�͑��݂ɖ����ȗ̈� |
�Ⴆ�u�Ȃ��l���l���E���Ă͂����Ȃ��̂��v�Ƃ������Ƃ��������̂Ɂu����͐_�̝|������v�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ����B���R�Ȋw�͊�]�≿�l�ƌ��т��Ă͂��Ȃ�����B
�@�@�����_�����݂��Ȃ��̂Ȃ牽������Ă�������Ă���B�i�J���}�[�]�t�̌Z��j�@�@
���m�[�́u�ϗ��ƒm���͍s����ʂ��ĕs��I�Ɍ��т����Ă���v�Ƃ����B
| �������̑̌n |
| �@�@�@�� �@�@�R �@�@�@�� |
| �q�ϓI�m���̑̌n |
| �m���Ɖ��l�̍����֎~�@�@�@ �@�@�ϗ��I�s�ׂƂ��đI��������� �@�@�m���̗ϗ��Ƃ�������݂̂�����Љ�Ɨ������� |
�@
�ϗ��Ƃ́E�E�E
|
�ϗ��Aethic�A�������Ƃ������t�Ɍ��X���z�I�v�f�͂Ȃ��B
�����牽�Ȃ̂��Ƃ������ƂɂȂ邪�A�ϗ��ɂǂ�������b�Â������邩�Ƃ������Ƃ����Ȃ̂ł���B
��ʓI�Ɂu�ϗ��v�ɂ��Č�鎞�A�u�_����^����ꂽ�|������v�Ƃ������z�I�ȕ����Ō��ƌ����ڂ͂���B�������A�u����͐l�Ԗ{���̂����������v�Ƃ����A���z�I�v�f���������܂Ȃ��l�������\���ɂ��肦��̂��B
���m�[�������m���̗ϗ�
| �^�̒m���� |
���z�I���l�ł���A�l�Ԃ�����̑I���ɂ���Ă���ɕ�d����B |
| �m���̗ϗ��� |
���z�I���l�ݏo�����̂Ƃ��Đl�Ԃd����q���[�}�j�Y���ł���B |
�@
���m�[���_�̞B����
| �k�������̈ӌ��l ����܂ł̃��m�[�̖����ȕ��q�_���炷��ƁA�u�m���̗ϗ��v�₻�ꂪ�^�̎Љ��`��z���Ƃ����悤�ȍl�����͂��������ł͂Ȃ����B |
| �k�������̈ӌ��l ���m�[�͎��Ɠ����Ɋׂ��Ă���B�ނ͘_����ςݏグ�Č��_�ɓ��B����Ƃ����`���ѓO�ł��Ȃ������̂��B |
���q�����w����Љ��`�������o�����Ƃ͂ł��Ȃ��B���̂��߂Ƀ��m�[�̗��_�͂���B���ɂȂ��Ă������B�������A���ꂾ�����m�[�͐����������̂�������Ȃ��B
| ���m�[�̏o������� �l�Ԃ̈�`�I�������l�Ԃ̐��_�̂��Ȃ�̕������K�肵�Ă���B ���̂��ƂŐl�Ԃ͑��l�ȕ������I�F�����߂ݏo���A���Ȓ��S�I���z�̖��ɐZ���Ă����B ���̌��z��j�鎩�R�Ȋw�̗͂ŐS�n�悢���͔j����B �����Ȃ�Ȃ��悤�ɐl�X�͋q�ϐ��̌����������Ɍ������Ȃ��悤�ɂ��Ă����B ���l�̗̈�ɗ�������Ȃ��悤�ɂ��Ă����B ���̍s����͈Í��̓ޗ��ł���B |
| �����A���m�[�͎����̏o���������������Ƃ͂ł��Ȃ������B |
�_�ɋF���ĎE��
�����̐l�������Ƃ��鎞�u���R�Ȋw�v���u�_�v�̕������ʂ͑傫���B�u�_�v�̕����l�����₷���B
�ߑ�ɂȂ��Ēm���l���u���̂����_��@���͏�����v�ƌ��������A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ������B�A�����J�ł���ʑ�O�͎��R�Ȋw�I�ȕ��̌����ł͂Ȃ��u�_���܂�@���v�Ƃ����悤�ȗ͂Ő����Ă���B����ł����̂��낤���H
�����̃��V���A�L�A�����ł͐_�̖��߂ňٖ��������ׂĎE���B���̂�����̂��ׂĂ��E���A���̖��߂ɏ]��Ȃ��҂��E�����B�_�ɋF��F��قǎE���͕��R�Ƃł����B
| �Q�l�F���V���A�L��� |
| �����V���A�͖��Ɍ������B�Ƃ��̐��������Ȃ����B�傪���̒������Ȃ������ɗ^���������������炾�B�i6��16���j |
| �����̒��ƒ��̒����ׂĂ̂��̂���̂��߂ɐ��₵�Ȃ����B�i�E���Ȃ����j�i6��17���j |
| ����̓��V���A�ɋ���ꂽ�B�u����Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̂̂��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�키���S����A��ăA�C�ɍU�ߏ��B����B���̓A�C�̉��Ƃ��̖��A���̒��A���̒n�����Ȃ��̎�ɗ^�����B �i8�� 1���j |
| ���C�X���G���͔ނ��ǂ��Ă����A�C�̏Z�������Ƃ��Ƃ��r��̐��ŎE���A���̐n�Ŕނ����l���c�����|���Č�A�C�X���G���̑S���̓A�C�Ɉ����Ԃ��A���̒������̐n�őł����B�i8��24���j |
| �����̓��ł��|���ꂽ�j�⏗�͍��킹�Ĉꖜ���l�ŁA�A�C�̂��ׂĂ̐l�X�ł������B�i8��25���j |
| ���������ă��V���A�͂��̑S�y�A���Ȃ킿�R�n�A�l�Q�u�A��n�A�X�Βn�A���̂��ׂẲ���ł��A��l�������c����̂��Ȃ��悤�ɂ��A���̂�����݂̂͂Ȑ��₵���B�C�X���G���̐_�A�傪������ꂽ�Ƃ���ł������B�i10��40���j |
�u�l���E���ȁv�Ƃ������Ƃ͒��ۓI�ɂ͌����邪�A���Ƃ͕K���l���E���B�l���E���Ȃ����Ƃ͂Ȃ��B
�A�����J�ɈڏZ�����l�X�����Z�����E�����B�F��Ȃ���E�����B�F�炸�ɎE�����Ƃ͂ł��Ȃ����炾�B
����̐_�͋Ɉ��̐_�ł���B
�@�Q�l�}���F�w�L���X�g���̕s���e�x�n�ӈ�v��
�@�@�L���X�g���͊��e����������͕s���e�ł���B
�L���X�g���k�͗B���̐_�ƌ������A����͗B���̐_�ȊO�̂��̂ɑ��Ă͐�ΓI�ɕs���e�Ƃ������Ƃł���B�l�Ԃ̔��f�͞B���ł��邱�Ƃ�F�߂Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂Ɂu�B���̐_�v��M���Ă���B
�l���ق��̂͐_���H
�l�Ԃ͐l�Ԃ��ق��Ȃ��B�������A�ق������Ȃ��B
�����ł��邩�炱���A����A�ɂ�������炸�A���͎҂́u�@�����̂͐_�ł���v�Ƃ������������D��Ŏg���Ă����B
| �Q�l�F���[�}��12��19�� |
| ������l�����A�����ŕ��Q���Ă͂����܂���B�_�̓{��ɔC���Ȃ����B����͂��������Ă��邩��ł��B�u���Q�͂킽���̂��邱�Ƃł���B�킽����������A�Ǝ�͌�����B�v |