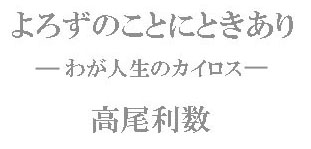
法政大学社会学部 最終講義
(2001年1月12日)
| P.1 |
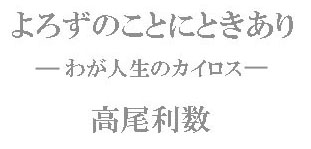 法政大学社会学部 最終講義 (2001年1月12日) |
|
|
天(あま)が下の萬(よろず)のことには時あり。生まるるに時あり、死ぬるに時あり、植(うう)るに時あり、植たるものを抜くに時あり、… 黙するに時あり、語るに時あり、… 泣くに時あり、笑ふに時あり、… 保つに時あり、棄つるに時あり、… 戦ふに時あり、和らぐに時あり。(『伝道の書(コヘレトの言葉)』3:1−8) 旧約聖書はヘブライ語で書かれている … ヘブライ語の「とき」を表わす語「エース」は、神との関わりのただなかで「打ちかかる」具体的な出来事を意味する … だから「今」(パアム)も、「瞬間」(レガ)も本来「打撃」「打ちかかり」を意味する「脈動」的概念である … この「とき」理解は、ギリシア語では「カイロス」 kairos と訳されたが、それは「切断する」という動詞に由来するもので、誕生や死、決定的な出会い、社会的大変動のような重大な経験に用いられる … それに対してギリシア語の「クロノス」chronosは等質で持続的な時間概念である→ chronic(慢性的), chronology(年代記) … 「時」という漢字は、一日が寺の鐘の音で刻まれるような等質な、いわば時計的な時間を表現するもので「クロノス」に呼応する。そうした平板な概念に対して、古人は決定的で「切断」的な経験をした場合には、農耕民にとってはまさに生死にかかわる「秋」という字を用い「とき」と読ませた。…例えば「本土決戦の秋(とき)」というふうに。… まさにギリシア語の「カイロス」に呼応する理解である。… 今、私にとって法政大学での26年以上にわたる「時(クロノス)」が終わるに際しては、折り目・節目に出会ったさまざまな出来事に、いわば実存的な「秋性(カイロス)」を感じる。わが生涯には、なんと多くのカイロスが与えられたことだろうか、と! |